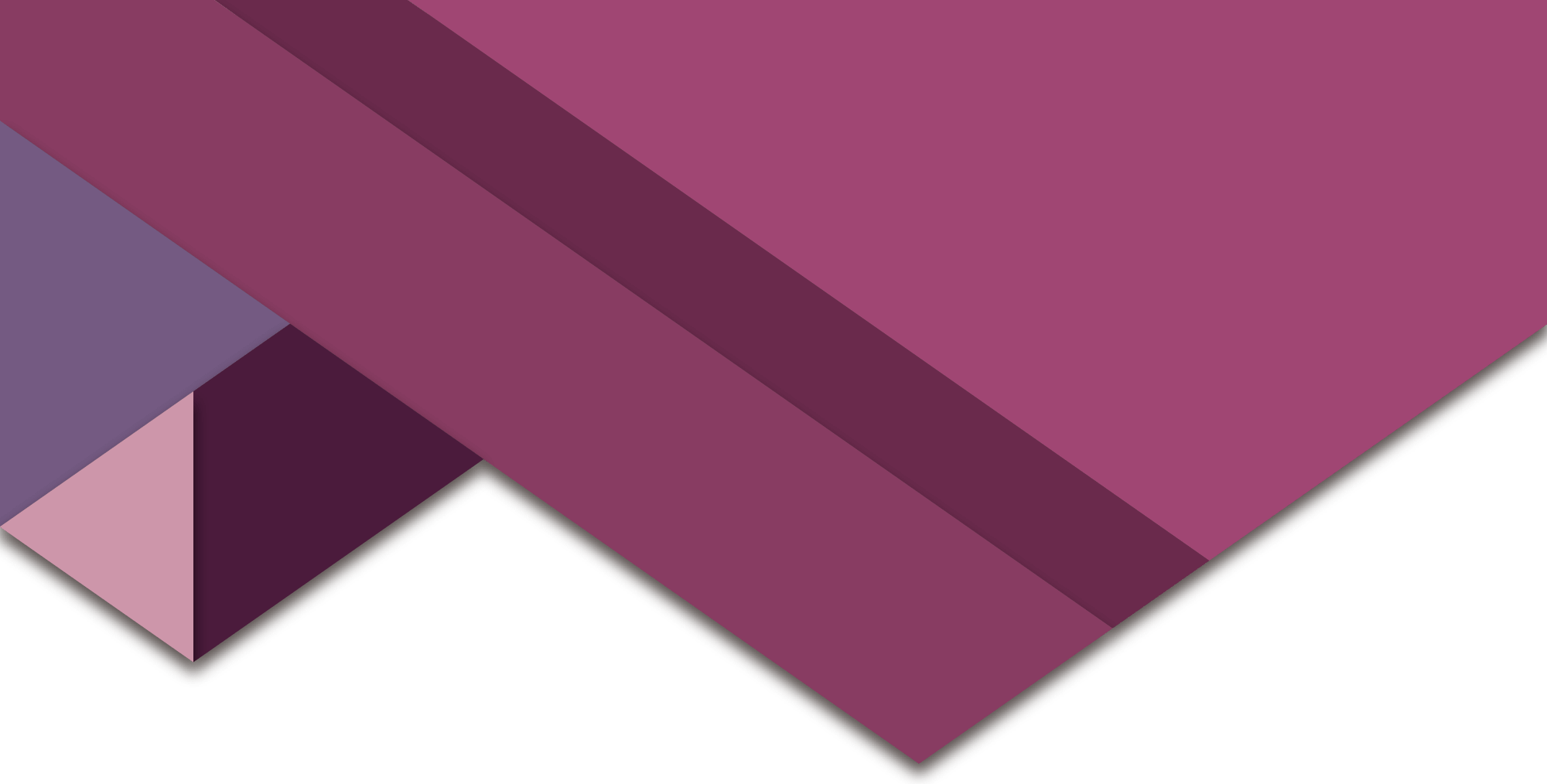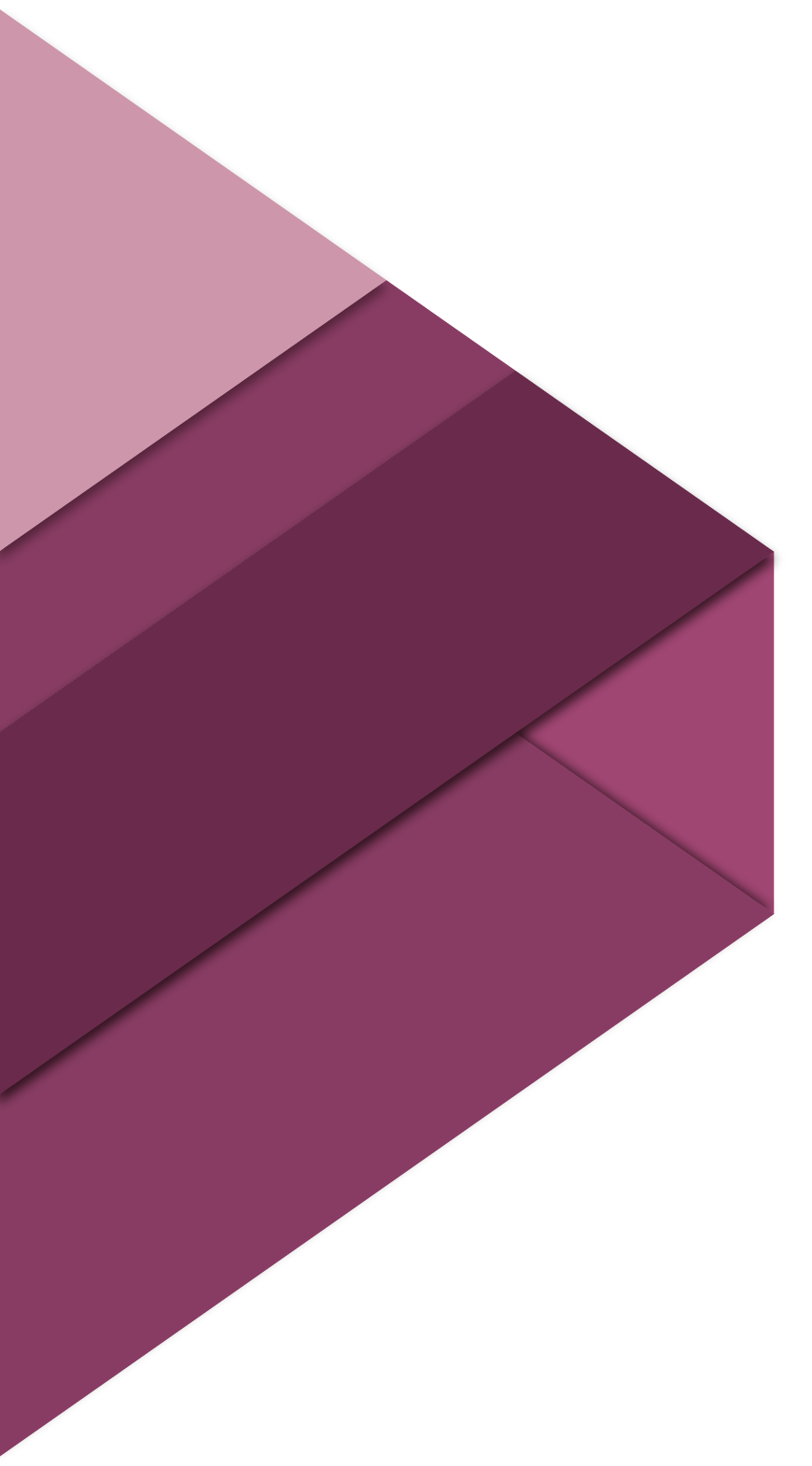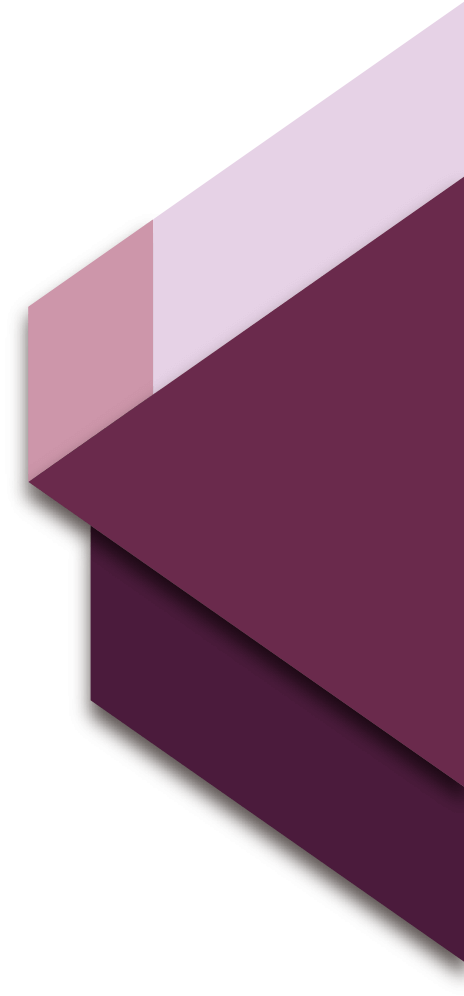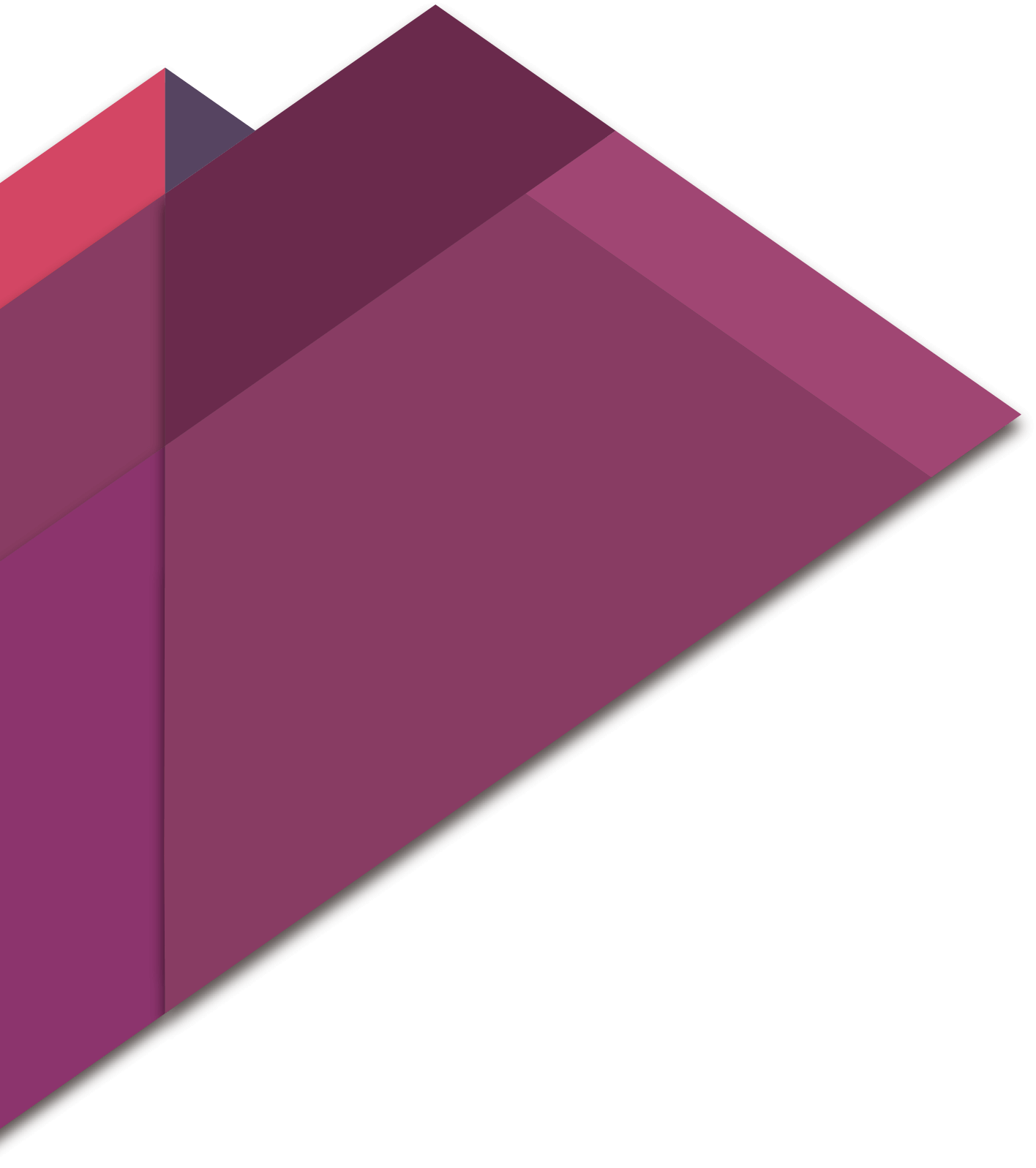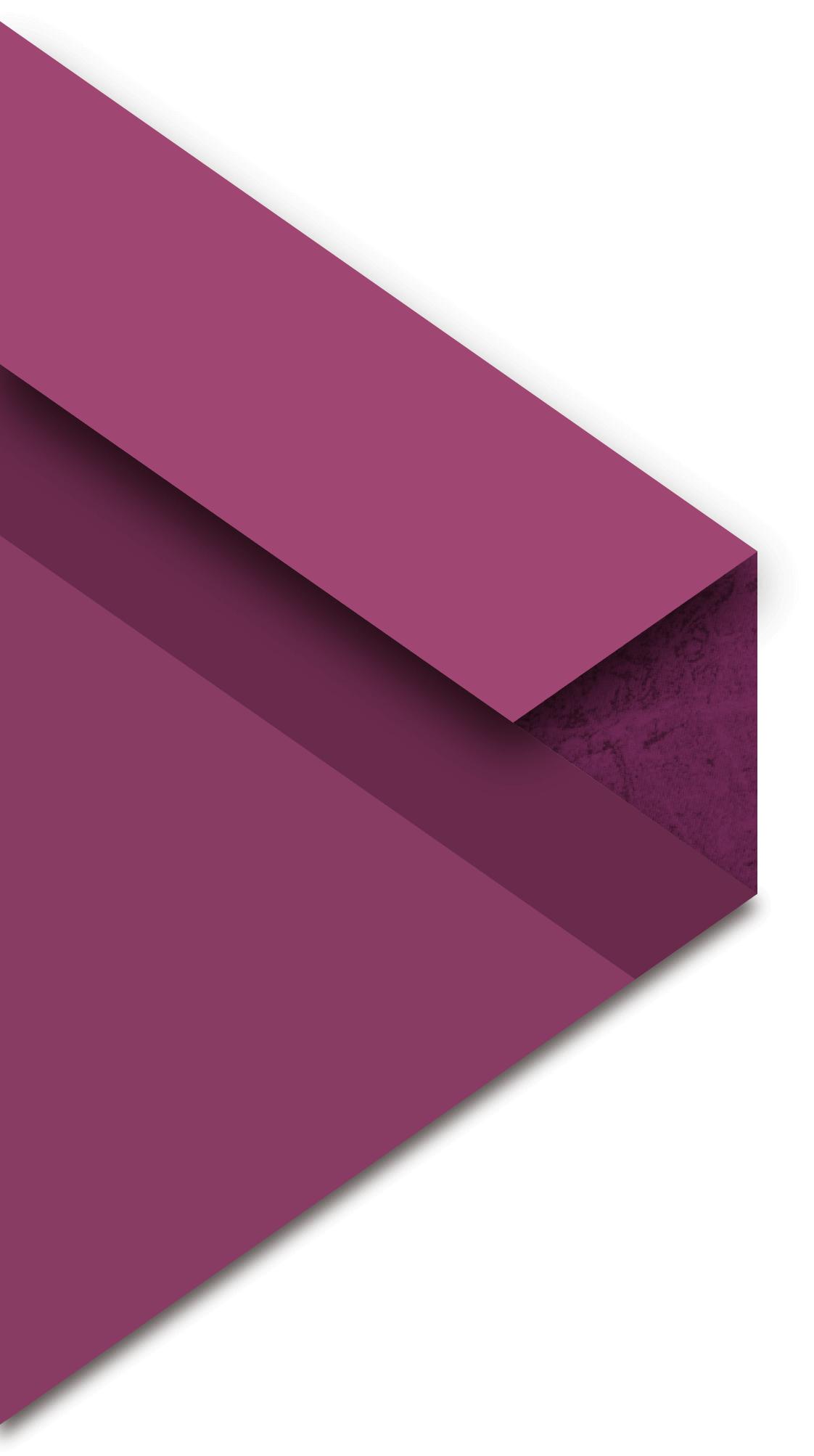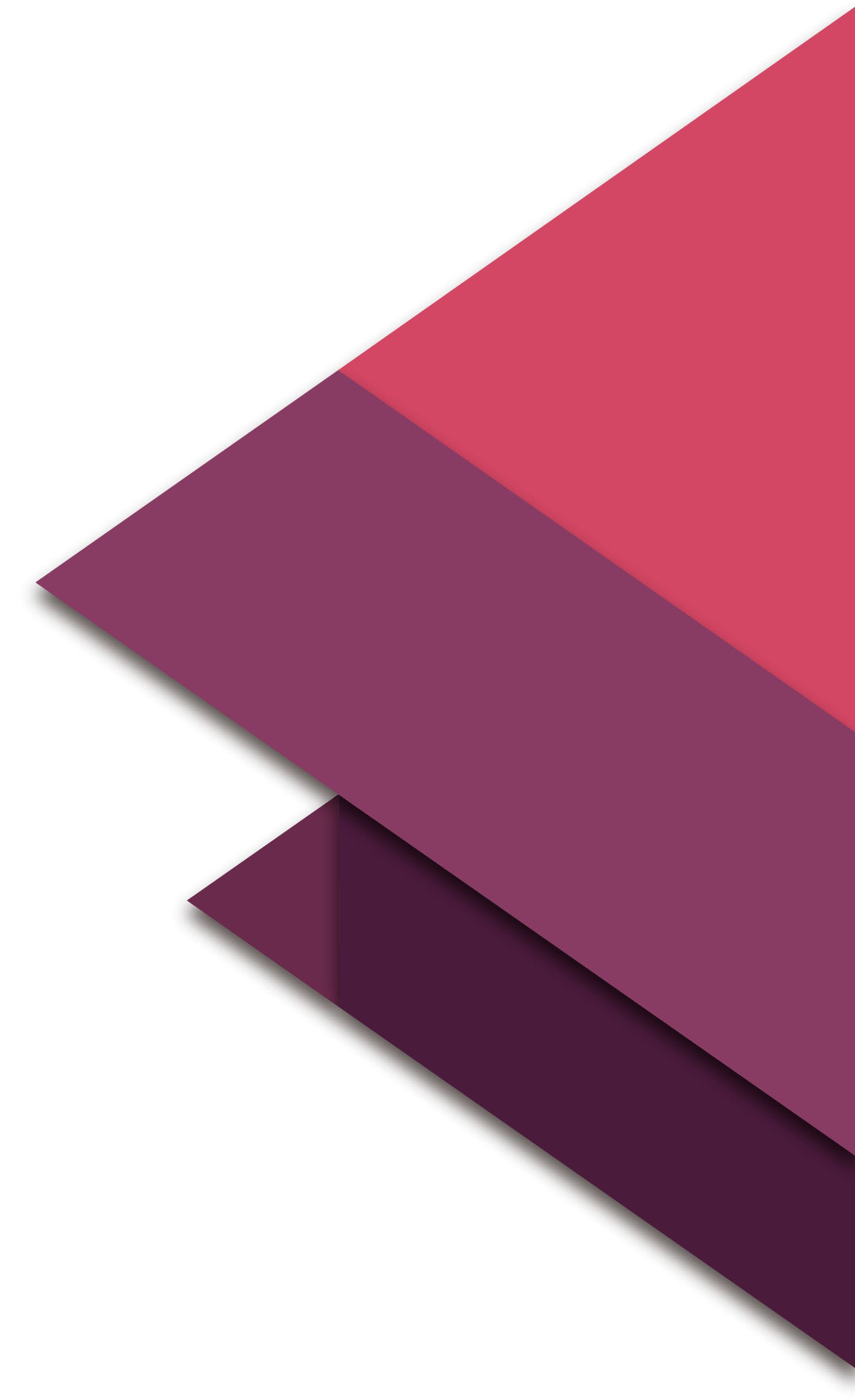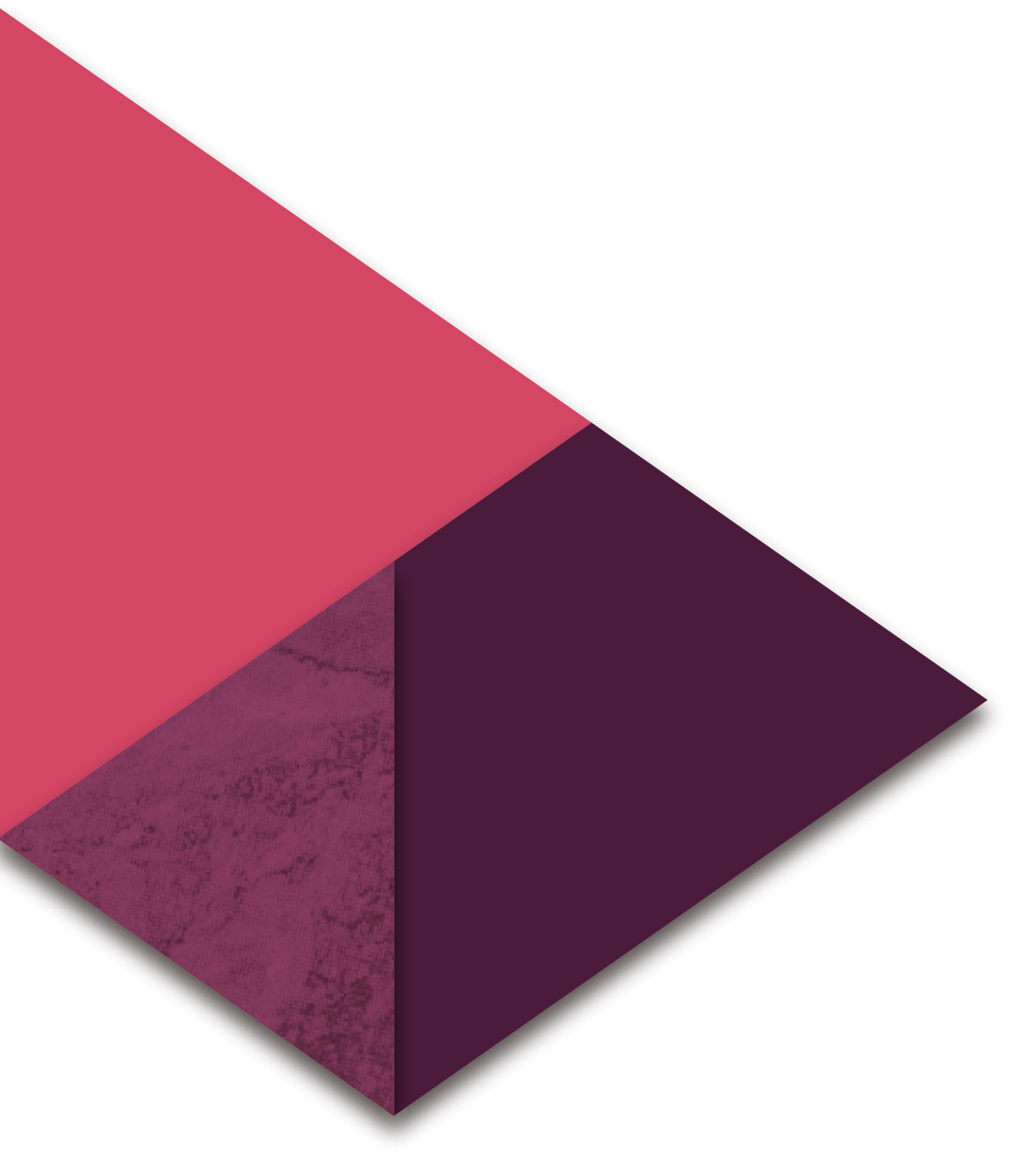テクノロジーの世界はまさに日進月歩であり、次々と新しい技術、サービスが生み出されています。革新的なイノベーションは人類に大きな利益をもたらす一方で、それらは実社会の倫理観や価値観とすれ違ってしまうことも少なくありません。
この期待と不安の入り混じるテクノロジー界を、グローバルな視野のもとファシリテートしてきた1人が、ICFプログラムコミッティーの伊藤穣一MITメディアラボ所長。過去のICFにおいても、「デザインの素養を持ったエンジニアの必要性」や「人間の機能拡張」、「デザインされた共生の世界」など、テクノロジー開発が抱える課題と向きあう際に有用な視点を提案してきました。
ICFを通じて都市社会を議論するムーブメントを起こしたいと願う伊藤氏に、今日のテクノロジー開発を加速させるために必要な視点や、昨年のICFの手応え、そして今年のICFへの意気込みについてお聞きしました。

顧客中心主義を脱却した真のユーザーセントリックデザインとボトムアップアプローチの重要性
「デザイン」の視点でその課題を説明してみましょう。なぜなら、テクノロジーを開発している会社は、「テクノロジーをデザイン」している会社とも言うことができるからです。今日の多くの会社はカスタマーファーストという原理に基づいたビジネスを展開しており、ある意味で分かりやすいユーザーセントリックデザインの形をとっています。しかし、必ずしも顧客だけがユーザーなのではなく、社員なども含めたステークホルダー全体をユーザーと定義することができます。また、実際に、お金をくれる顧客だけを対象にテクノロジーをデザインすると、システム全体が弱体化するという問題も生じてしまいます。そのため、企業活動によって生じる社会的コストや被害というものを自分の見えない部分に押し付けて、カスタマーファーストに徹するのは賢明ではありません。エコシステムや都市といった単位でコラボレーション、コーポレーションしていくような、より広い視野を持ったユーザーセントリックなシステムを開発することが重要なのだと考えます。
もうひとつ重要なことは、企業による適切な需要想定です。例えば、酔っ払っているときには誰もが「もう一杯お酒が欲しい」と思うわけです。でも、次の日の昼間の自分はお酒を欲しくないかもしれない。つまり多くの人にとって、欲しいと思っている物が、本当に今必要な物なのかどうかは考える余地が大いにありえるのです。現代社会には様々なプロダクツが溢れていますが、多くの企業は中毒性や瞬間的な購買意欲というものに付け入るスキを見出している側面が大きい。企業は本来、中長期的に個人や社会の本当のニーズを考えてサービスをデザインするべきですが、その時売れるものを売るという考え方に偏ってしまっているように見受けられます。これはテクノロジーを開発・活用する側の企業が意識的になるべき課題です。例えば、Facebookのユーザーが必要としているのは、本当の民主主義やリアルニュースですが、フェイクニュースの方が拡散されてしまったりしますよね。これを解決するためには、ユーザー自体がデザインに参画することができるパーティシパント・デザインという考え方が重要でしょう。これは都市開発などにも援用できる考え方で、都市開発をする側や建築家がトップダウンで行っていたものを、もう少しボトムアップなアプローチに変え、さらにフレキシブルに考えることで、都市が抱える様々な問題の改善につながっていくと考えています。

「文化」が倫理観、価値観を変え、そして企業を変える
近年、比較的若い人たちを中心に、倫理観に基づいてテクノロジー開発を行う人が増えています。目立った事例としては、Googleが軍事技術として人工知能を売ろうとした際に何千人ものGoogleの従業員が反対運動をしましたよね。これは、Googleほどの大きな会社でも、多くの個人の意思によって成り立っていると考えることができます。昔の日本の製造業なども同様で、現場のナレッジや美学がプロダクトにうまく反映されていました。このように、大企業のようにある程度トップダウンの環境にあっても、顧客と社員を含むコミュニティ全体が意識的になることで、ステークホルダーの倫理観を企業活動に反映させることができます。
そうですね。ある企業がカーボンクレジットなどを数値化することによって、自分たちの会社がどれくらいの影響を自然環境に与えているかを知り、それを改善することは可能でしょう。しかし、会社の理念を変えるほどの大きな変革を起こしたいような場合は、顧客や社員一人一人の倫理観や価値観そのものが変わる必要があります。そういった意識の変化を引き起こしうるひとつの手段としては、アートや音楽といった「文化」というものが挙げられます。1960年代のヒッピームーブメントなどは、文化が人々の価値観を変えた良い例なのではないでしょうか。

身体拡張に対する理解を加速させるには、アーティストの果たす役割が大きい
「障害をなくす」という切り口は医療分野でも昔から活発に議論されてきましたが、「身体拡張」となると途端にタブーになりがちです。最近、僕は「障害者」という言葉は「拡張者」と言い換えることもできると思っています。過去にはマーシャル・マクルーハンが「拡張はどこかに障害を伴う」というようなことを言っているんですね。つまり、拡張と障害はトレードオフの関係であると。
携帯電話は非常に自然な形で行われている拡張のひとつだと言えるでしょう。注目すべきは、携帯電話をずっと見ている人もいれば、そうでない人もいる、つまり身体拡張というものも、あくまで個人の選択肢のひとつであって、自身の環境のデザインの自由の範囲と捉えられる点です。今後は拡張にかかるコストはどんどん下がり、その種類も増えていくことは容易に想像できます。しかし、それを社会実装するためにはまだまだ多くの実験と理解が必要なことは確かです。ボディーハッキング※1など、トランスヒューマニズム※2な発想によって寿命が大きく延びたとしたら、それを社会が受け止められるようにならなければならないでしょう。
※1 身体のはたらきをより詳しく知るために、体内にRFIDチップを埋め込むなどの身体改造をすること。
※2 身体とテクノロジーの融合を通じて、前例のないレベルに人間を進化させようという思想。超人間主義とも訳される。
そうです。新しいものは文化の中でテストされて、社会のなかで役に立つことで初めて受け入れられるものです。体外受精を思い出してください。40年ほど前までは、まるでフランケンシュタインのようだと言われ、まったく受け入れられていなかった。それが今では保険が適用されるまでに社会に浸透しました。これは、社会にとって有用だと長い時間をかけてテストされてきた結果です。そして、その過程のなかでアーティストと呼ばれる人たちの果たす役割も大きいと考えています。
障害、身体拡張というものに関しては、近年ヴィクトリア・モデスタなどのアーティストが活躍していますが、そういった活動がパブリックの見る目を変えていきます。印象的だったのは、2016年にリオで行われたパラリンピックの閉会式です。日本がプロデュースしましたが、非常にスタイリッシュでカッコいいものでした。共通するのは、「障害を乗り越えて何か新しいことができるようになる」といった従来の考え方を凌駕するほどの世界を表現したことです。アーティストには人々の意識を変える力があります。

人類が直面する中長期の問題を解決するために必要な哲学、倫理の議論
テクノロジーを突き詰めていくと、どうしても「教育」や「哲学」に考えを巡らせることになります。我々はなぜ生きているのか、といった根本的な問いにぶつかるんです。テクノロジーによって問題解決をしようとか、より良い世の中を作ろうと言うのは簡単なんだけれども、「誰のために」「どれくらいの時間軸で」良くするかを具体的に考える必要がある。なぜなら、目的設定によってやるべきことは全く違ってくるからです。例えば、環境問題を考えてみると、数世代にわたってゆっくりと環境破壊が進んでしまっています。みんなの目の前で、進んでいる環境破壊を誰も止めることができない状況なんですね。これは、人間社会が環境破壊に対して設定している時間軸が短すぎることが原因のひとつと考えられます。人類が直面しているロングタームの複雑な問題を解決するためには、一度、そもそも論に立ち返って議論を進めなくてはいけないのではないでしょうか。だから2018年のICFでは哲学を語れる人と議論がしたかった。それこそが今のテクノロジー開発に必要とされる視点なのだと思います。