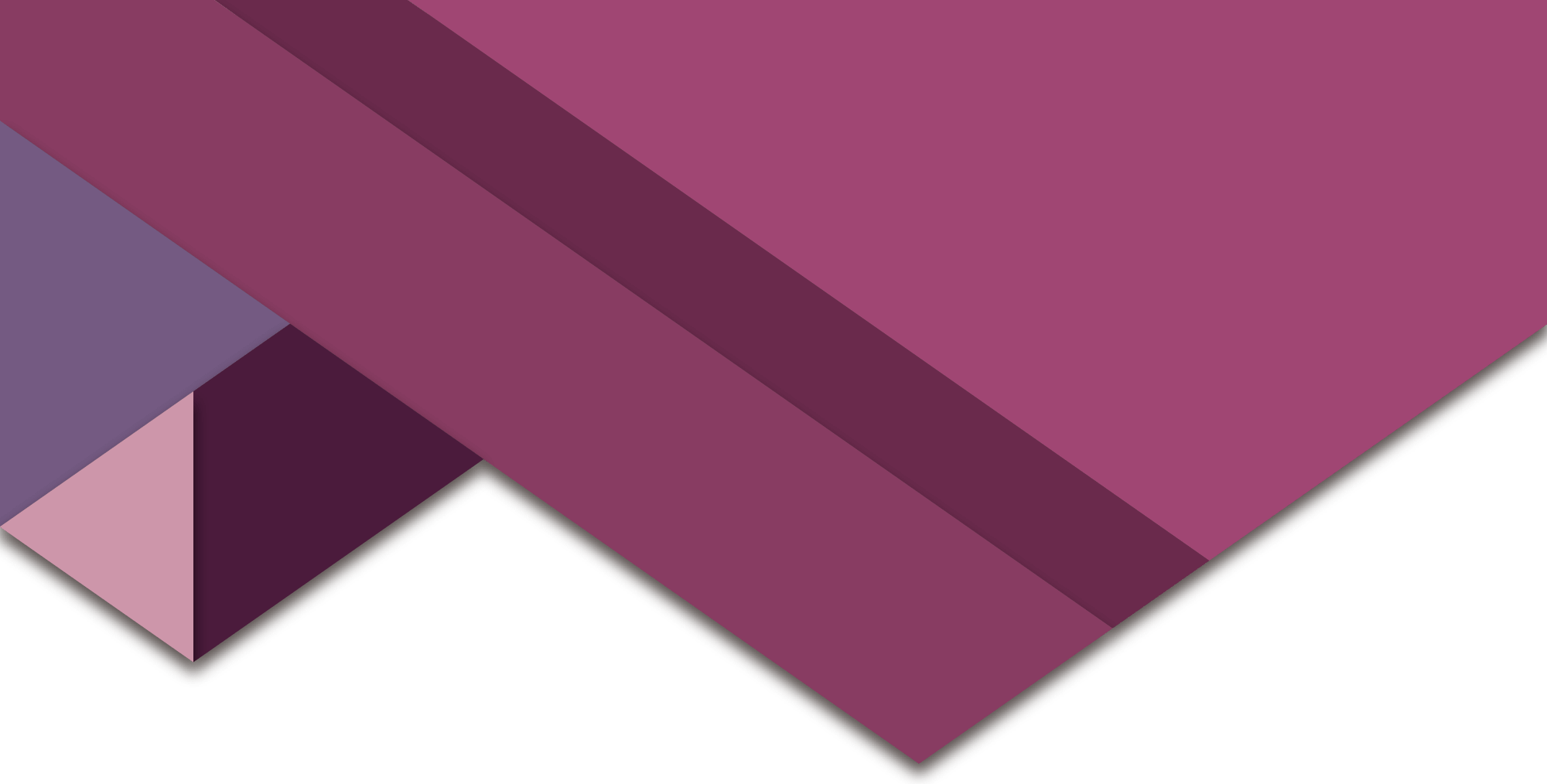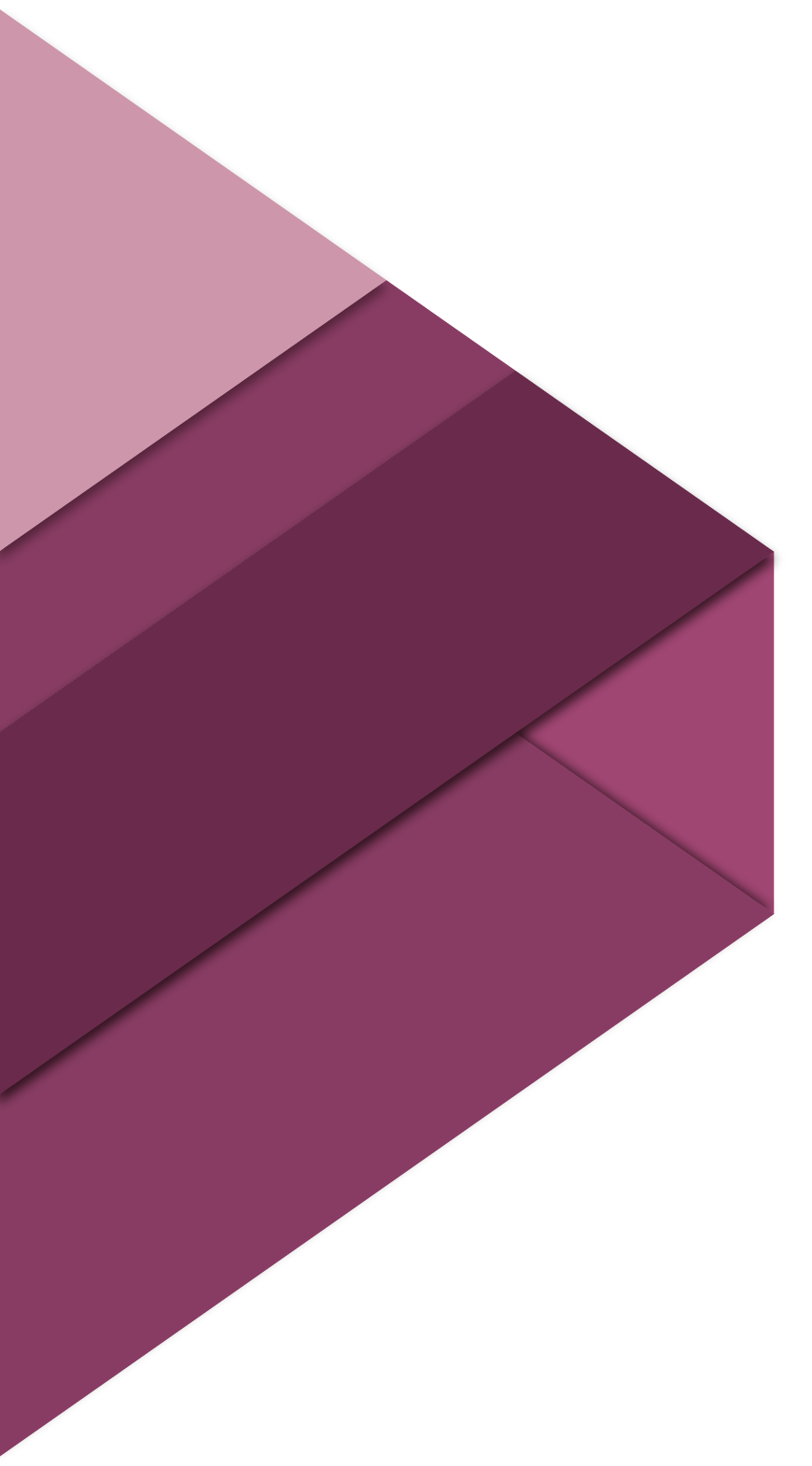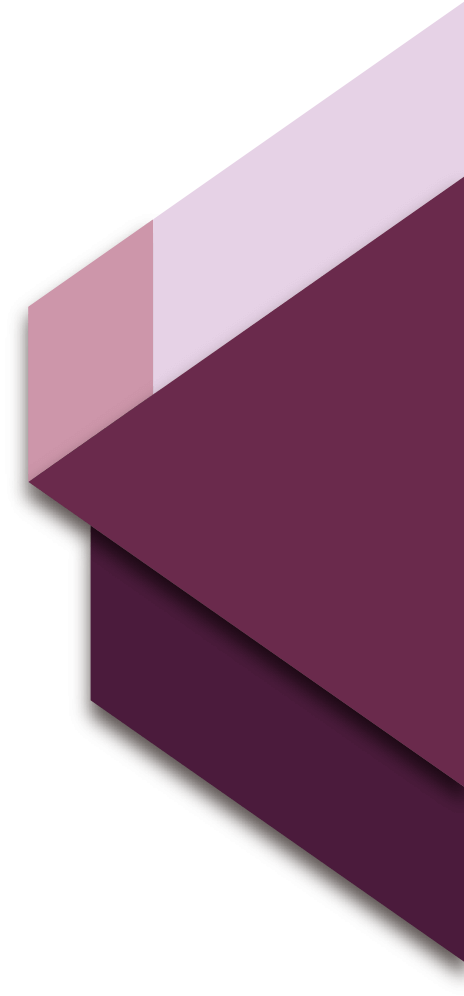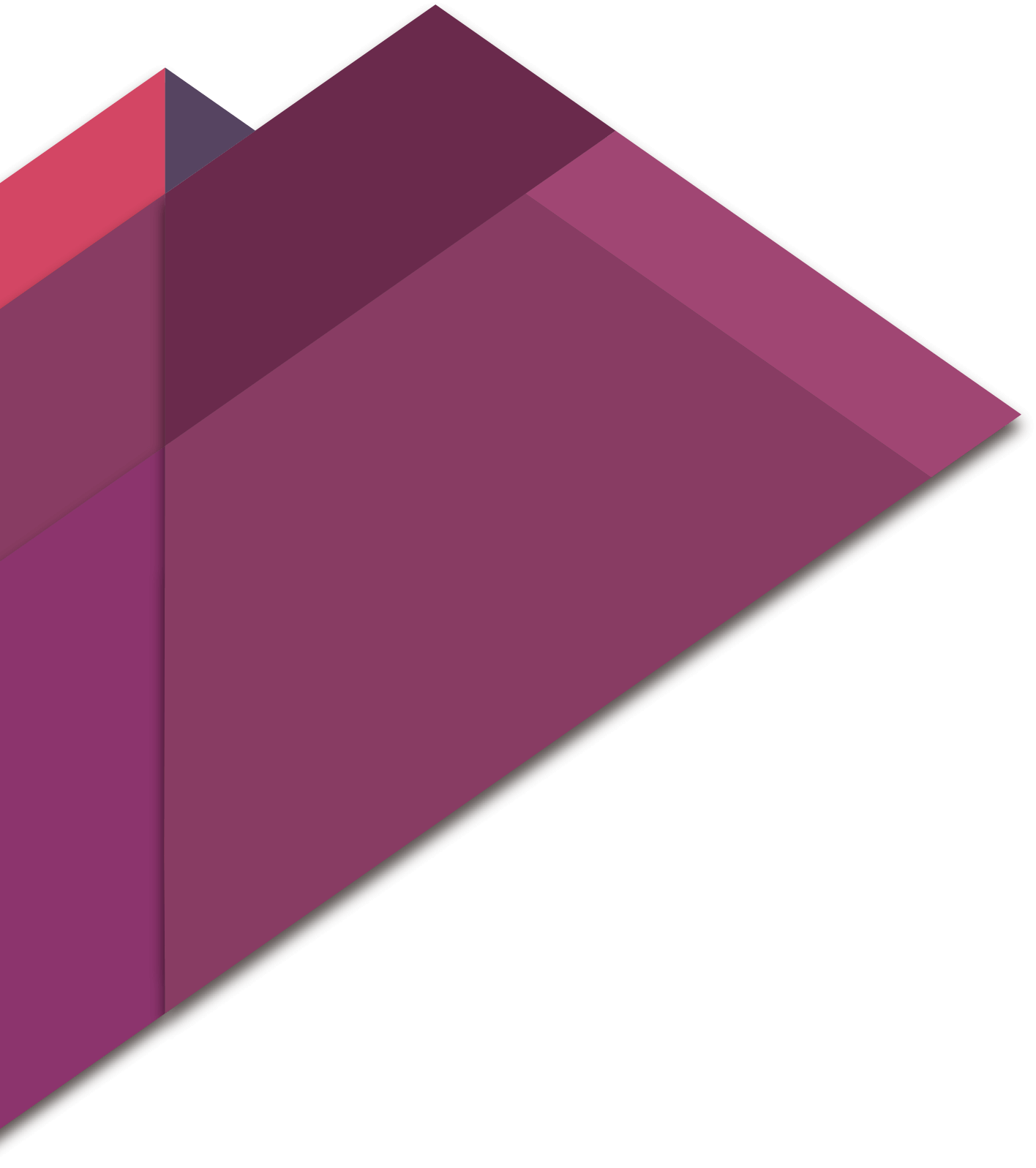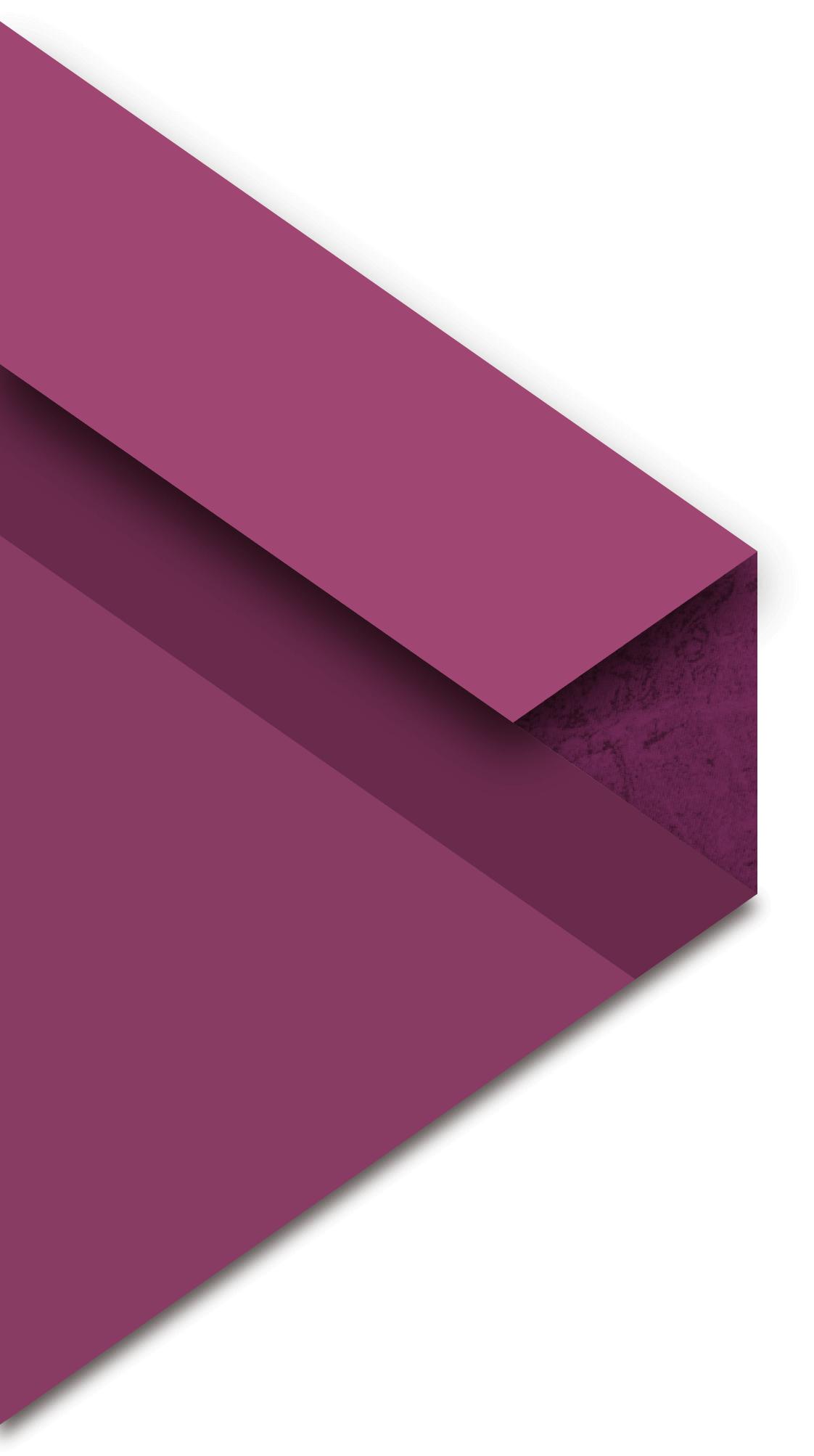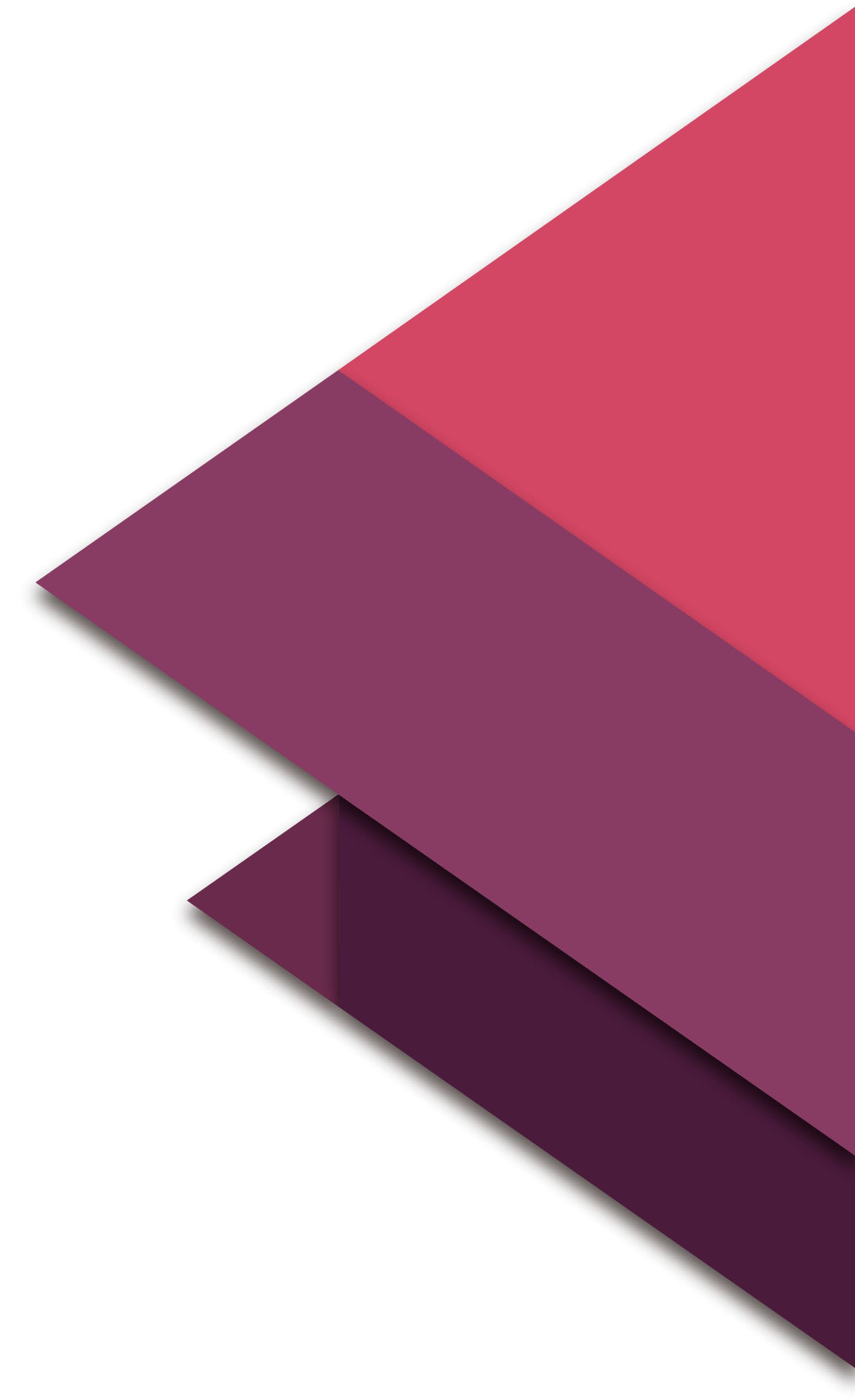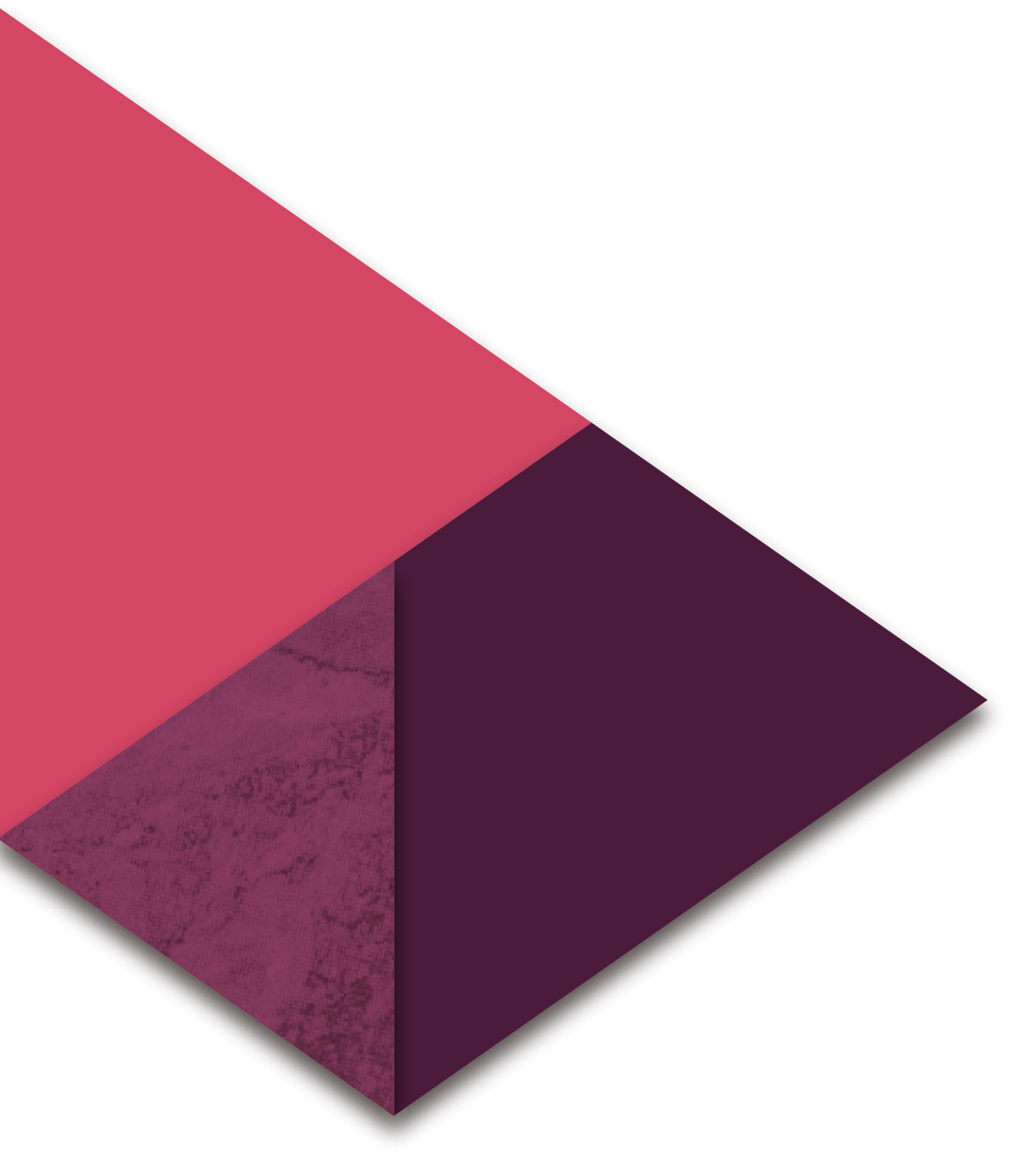今、多くのビジネスパーソンが、論理的な思考だけでは進展しないビジネス課題に直面するなかで、アートの直感的な思考回路や非言語的な物語性に注目しています。アーティストの現実認識を通じて、新しい世界の見方を獲得しようとしているのです。
日本において、現代アートの間口を広げ、アーティストの可能性や現代アート作品の楽しみ方をビジネスパーソンに紹介してきた1人である森美術館館長の南條史生。今まで、宇宙建築やバイオアートなど先端的かつ異色のクリエイター・アーティストたちを世界より呼集し、経済や都市領域のビジネスパーソンたちにインスピレーションを与えてきました。
ICFの「アート&サイエンスセッション」のモデレーターである南條氏に、アートとサイエンスを結合させる時代背景やその重要性、今年のICFの見どころ、クリエイティブ都市・東京に必要なことについて尋ねました。

異分野同士がリテラシーを等しくして進むべき時代が来た
ICFは元々、都市計画関係者や科学者、クリエイター、アーティスト、建築家などが集まって意見交換するという発想で設けられた場です。当初のキャッチコピーは、「クリエイティブ・ダボス」でした。その時代背景として、アジア各国の台頭が目覚ましく、日本はもはやマスプロダクションでは戦えない時代になったことが挙げられます。日本が今後勝負できるフィールドは、創造性を源泉とするクリエイティブな仕事しかないという現状認識から出発したのです。
その際、重要なのは、様々な分野のオピニオンリーダーが集まること。それぞれの分野で使っているリテラシー、つまり言語や現実認識は相当違っているので、もしリテラシーを等しくして1つのテーマを協働して議論していくことができれば、それは内容も充実し、クリエイティブ産業の中心は東京だというふうになっていくのではないか、と思ったわけです。実際に、学術の世界では、違う領域と思われていた学問同士を対話・総合させる「Interdisciplinary(学際的と訳される)」の動きが盛んですし、アートの世界でも、「アートと技術」「アートと食」、「アートとファッション」などという形で、異分野同士が結びついて新しいものを生み出そうとしています。
様々な組み合わせが考えられるなかで、ICFで注目しているのはアートとサイエンスという異分野の新結合です。アートは非常に直観的な世界、そしてサイエンスは科学的に論証しながら進む世界。一見全くの別ものですが、結局のところこの2つは非常に近いものと言えます。それはどちらもこの世界の現実はどういうものなのかという哲学的問題認識を共有しているからです。アートとサイエンスのそれぞれの分野で先駆的な考え方を持つオピニオンリーダーたちを同じ場に集め、新しい世界観や人間が生きることの意味などについて議論して、20年先に我々はどう生きていくのかについて、示唆ができれば素晴らしいでしょう。それこそが、クリエイティブな仕事の発端になるはずです。さらに、アートとサイエンスの力が最も発揮できる領域の1つが、都市開発ではないかと考えています。都市開発とは言うなれば巨大なものづくりであり、研究開発の結晶で、なくなった森稔会長はそれは「アートだ」と思っていたようです。20年後の都市を見据えながら、このように異分野の人たちを結集して、新しいヴィジョンを提示するのが「アート&サイエンスセッション(以下、A&S)」の醍醐味です。

サイエンス&テクノロジーの用途や極限を、分野を越えて議論する重要性
一般的なビジネスカンファレンスでは、どうしてもアートやサイエンスよりもテクノロジー主導で議論が進みがちになってしまいます。アーティストというのは元々言語でプレゼンテーションする能力がそれほど高くありません。彼らは、パワーポイントではなく、自分の作品を通してある種の見解や提案を出していくということをしているからです。ビジネスパーソンとアーティストと話がかみ合わないなと思える場面が多々ありますが、そこにも共通言語がないという問題点が見え隠れしていると思われます。
非常に大事なポイントは、アーティストたちはアートの使い方や実用化なんか考えていないということです。もっと根本的なものの考え方をしている人たちなので、他分野の人達にとって目からウロコの意外な発想が飛び出してくることも少なくありません。それはアーティストに限らず、科学者も同じ。彼らは技術者とは異なり、科学の使い方を考えながら研究をしている訳ではないんです。だからこそ、A&Sには、アーティストや科学者以外の人が積極的に参加し、その最先端の作品や研究の成果を知ると共に、活用を考える必要もあるのだと思います。
まず、身体から宇宙までという広い範囲において、先端的な研究者等を集められたことで、それぞれの最前線を把握することができました。特筆すべきは、サイエンステクノロジーは補完なのか拡張なのかという議論があったこと。かつては補完だと思っていたけれども、今やそれは拡張なのではないかという意見が出ました。「拡張」の具体例として、健常者より10センチも20センチも長い義足が作れるといったパラリンピック競技の話題があがり、パラリンピックとは一体何かというポストヒューマン的な議論にもつながりました。手応えとは言えないかもしれませんが、昨年、十分に語りつくせなかったということで、今年も同様のテーマで議論を深めようと機運が高まっているのは良い兆候でしょう。

江戸時代がヒント⁉ ポストAI時代の文化・ハピネスのあり方
技術革新は何のためになされるべきものなのか、というのが大きな問いです。科学の世界にはマッドサイエンティストみたいな人もいます。原爆もその一種で、作ってしまったことで人類を不幸にするという結果を招くこともあります。もう一度、何のために行動し取り組んでいるのかというところに立ち戻る必要があると思います。私と一緒にセッションリーダーをしている伊藤穰一氏でさえも、最近はインターネットには問題もあるというニュアンスが出てきています。今一番期待されていると言われている、ブロックチェーンやAI、バイオテクノロジーもそれぞれ危険や不完全さをはらんでいます。
一方で、資本主義や民主主義も順調ではありません。実のところ現代社会は、非常に危ういバランスの上に全てが乗っている状態なのです。だからこそ今、我々はテクノロジー開発の根本的な意義、その目的を注目しなければなりません。目的や目標が間違っているなら道筋を修正する必要があります。目標の持ち方を変えると、問い自体も変わるのではないでしょうか。そういったことを少しずつ議論しながら、いろいろなことに気付いていければ良いと思います。
AI時代に人間がやることは、基本的に文化とスポーツしかないと思います。シンギュラリティーに近い状態になれば、生産効率は上がるので人は生きるために働く必要がなくなります。そうすると次は時間をどう潰すか、という問題が生まれてくる。そのときに文化とスポーツしかなくなり、そこで人生の時間をそうしたことに費やす、その費やし方が重要になるでしょう。シンギュラリティー達成以降の人間社会は、モラルや生きる目標自体も違うものにシフトし、きっと全ての価値観もシフトするでしょう。そういう時代に向かって我々はものを考える必要があるのです。
これまでのハピネスは、一義的に富の蓄積や物質的な豊かさを指す風潮がありましたが、これからは変わってくると思っています。人間いずれ死ぬのであれば、生きている時間というものをどのように味わうのかということが大切です。どのように豊かに生きるかという価値観は、文化と密接な関係があります。そういう意味では、江戸時代はかなりハピネスが資本主義とは違う時代だったと思われます。300年近く平和が続き、多くの人が歌舞音曲、歌舞伎や浮世絵を楽しみ、お金がない人でも俳句などを楽しんでいました。身分に関わらず、上から下まで社会の構成員がみんな文化に浸っていました。トータルに見ると江戸時代こそがAIの時代の考慮すべき新たなモデル提案になるのではないかと思います。
これまでの経済や資本主義というものは、商品や不動産など目に見えるものを中心として動いていました。しかし資本主義の本質が変わってきたという兆候が既に見え始めています。アートを例にすると、観客は芸術作品そのものよりも体験を求めています。演劇でも、「イマーシブシアター」と呼ばれる、観客が様々なシーンに没入するという体験型演劇が流行っています。アートに限らず、ビジネスにおいてもユニークな物語、ユニークな可能性に投資をしているように見えます。資本主義の資本が規定する財、それはもっと広義のものになると考える必要があります。またその消費の形態分析には、もっと心理学的な要素が入る必要があるでしょう。今後、一回限りの体験がハピネスである、という価値観が浮上してくるでしょう。

ICFのカオスが日本の新しいアイデンティティーを生み出す
ICFの元々の発想はダボス会議ですから、我々が招待した人達だけが来るカンファレンスにはしたくないと思っています。あそこに行けば何かが手に入る、つまり人的ネットワークや自分の知らない新しいものの見方、最先端技術などを知ることができる希少な場として誰もが認識し、自然と人が集まる場になることを望んでいます。また、各登壇者はそれぞれの分野において非常に先鋭的な取組みをされている方をお呼びしています。そのため、彼らが、我々4人のコミッティーの視野を越えて、新しい経済・文化そして都市の形を活発に議論していくでしょうし、そのカオスのような場をつくることにICFの役割があるとも思っています。
さらには、アジアの中で最もクリエイティブな都市は東京であるという印象を国際的に形成できるカンファレンスにまで高めたいとも思っています。ICFが知られてくればクリエイティブの中心は東京にある、という認識が世界に広まるでしょう。そこに日本の新しいアイデンティティーが確立できる事を期待したい。
ICFの今までを振り返ると、開催が6回目を迎え、認知度もかなり高まってきました。しかし、アジア各国のデザイナーや建築家たちにはまだ知られていないのが現状です。あらゆる領域を超越し、クリエイターもビジネスマンもたくさん集まって意見交換し合う場になるという目標に近づくためには、今まで以上に大きな仕掛けが必要なのかもしれません。例えば、業種毎の強固なネットワークが確立しているコミュニティーのイヴェントと組んだり、他の特徴のあるイヴェントと同時に開催したりといった、ブランディングのアイデアを将来的にもっと検討してもいいのではないかと。まずは、今年のICFで皆さんと未来を見据えた、実りある議論を展開したいと思っています。